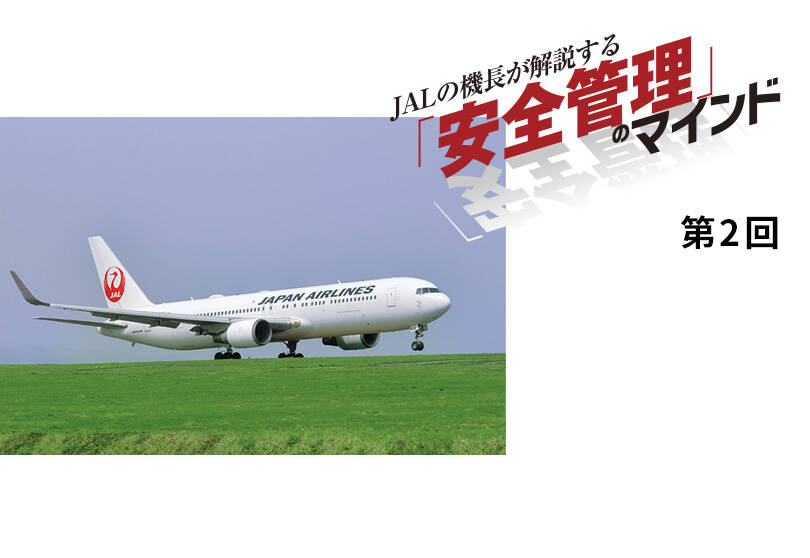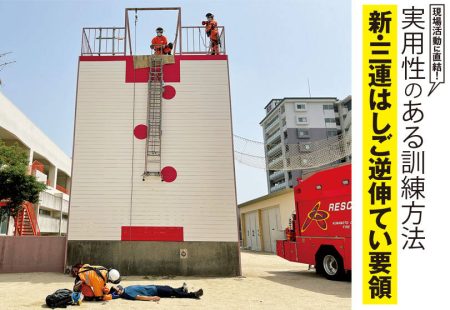Special
本邦初の指揮隊「伝令」マニュアル【前編】
東京消防庁狛江消防署が作成した指南書
今までにない教養資料の作成
このアンケート結果を踏まえ、伝令として必要な知識や無線運用、面積算定などを効率的に学べる教養資料を作成することにし、どのような内容にするか消防係の中で何度も話し合いを持った。資料を探すと、指揮隊に関する資料はいくつか出ているが、伝令に特化したものは今までなかった。また無線運用例等もあるが、現場で必要となる無線を入れるタイミングや、どのように状況を把握するかといった実務に関する部分について細かく説明している資料があまりなかった。そこで短編的な資料ではなく、「伝令としての心構えとは」から始まる、伝令の指南書的な資料を作成しようということになったのだ。
ポイントは次の3つ。
ポイント1:伝令の業務についてすべてを網羅する
伝令の仕事は無線を入れるだけではない、また大隊長の御付きだけではない、ということを知ってもらうために、伝令の業務のすべてを記載した。まず「伝令は最強のポンプ隊員」とし、知識や技術がどのポンプ隊員よりも優れていなくてはならない、という伝令としての気概を資料の冒頭に入れた。これは本来ベテラン伝令から叩き込まれるべき、伝令としてのあり方をまとめたもので、イメージのつきにくかった伝令員への理解を深めるためである。

ポイント2:知識と知識をつなげていく学習型資料とすること
伝令に必要な知識は消防業務の多岐にわたる。たとえば火災を例にとってみても、警防の知識や予防の知識、調査の知識、法律や規程の知識が求められる。こうした知識はそれぞれの量が膨大であることから、どこから学習を始めればよいかがわからない。このため、知識どうしを結びつきやすいように説明し、また自ら学習していく力をつけさせることが重要だと考えた。
たとえば「耐火造4/0共同住宅、4階401号室、ベランダの布団若干焼損にて鎮火……」という無線報告の中にも、耐火造はどのように見分けるのか? また、共同住宅の用途判定は? ベランダの布団が燃えたら何火災? というように多くの学習ポイントがあった。こうした点を効率よく学習していかなければ、単に無線報告ができるだけの伝令で進歩はないだろう。こうした知識が線で繋がってくると、実に現場での活動は楽になってくる。そのための学習の糸口を示したかったのだ。

ポイント3:読み物的な要素を取り入れる
伝令のすべてを網羅するつもりで資料を作成していけば、ページ数もかなりの量になることが予想されたが、文字の羅列だけではとても読まないだろうという意見が出た。そこで語り口調を主として、写真や図を多く取り入れるなど、読み物的な要素を取り入れようと考えた。興味を持って読んでくれる資料を目指したのだ。

完成した資料 「伝令のすゝめ」
各ポイントを抑え、様々な伝令経験者の話なども盛り込み、資料が完成した。資料は、福澤諭吉が自己の独立とそれをなすために学問の本質を説いた「学問のすゝめ」になぞらえ、伝令としての自立を目指してほしいという願いから、『伝令のすゝめ』とした。計196ページにおよぶ分量となった。