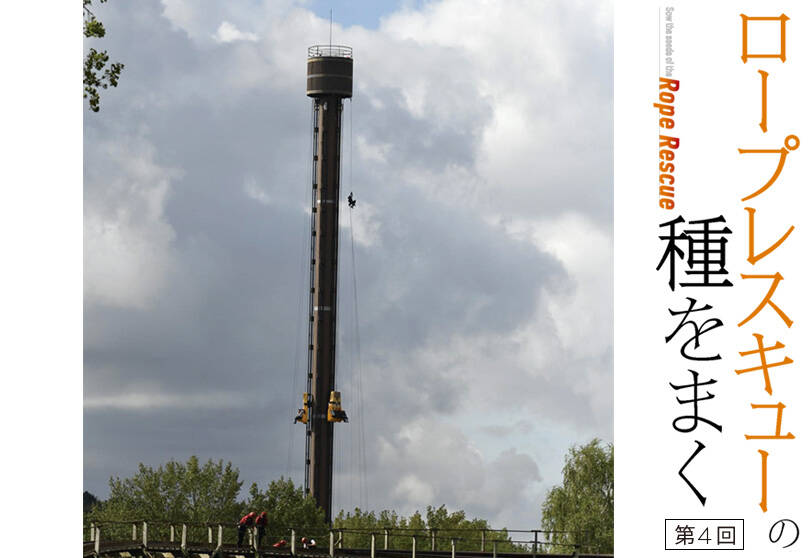Special
航空業界の常識「スレット アンド エラー マネジメント:TEM」
【連載】JAL機長が解説する「安全管理」のマインド 第2回
Jレスキュー2022年9月号掲載記事
前回(第1回)の記事はコチラ
エラーをしてもいいのか?
今回も本稿をご覧いただきありがとうございます。日本航空・ボーイング767型機機長の石川 宗(はじめ)です。
前回は「人間はエラーを起こす」と題しまして、人間には能力の限界があり必ずエラーを起こすという話をしました。さらにこのエラーは「認知」「判断」「行動」という、人間が行う情報処理の3段階すべてで発生する可能性があることもお伝えしました。いわゆる「ヒューマンエラー」についてご紹介したのですが、「エラーをしたら駄目じゃない?」と、疑問を持たれた読者の方も多いのではないでしょうか? おっしゃる通りです!
些細なエラーが重大な事態にまで発展する可能性がある航空機の運航では「人間だからエラーは仕方がない」では済まされません。そこで2回目となる今回は、航空機の運航の中で、『どのように「ヒューマンエラー」をマネジメントしているのか』についてお話をしたいと思います。
『スレット アンド エラー マネジメント』が生み出すもの
大前提ですが、「ヒューマンエラーをマネジメントすること」は、個人のエラーを“ゼロ”にすることではありません。繰り返しになりますが、人間はエラーを必ず起こすからです。裏を返すと、ヒューマンエラーの発生を前提に、航空機の運航を行う必要があるということです。
この「ヒューマンエラーを前提に、航空機の運航を行う」ための考え方が、『スレット アンド エラー マネジメント(TEM:Threat and Error Management)』というものです。少々耳慣れない言葉かもしれませんが、航空業界では広く浸透している考え方です。今回はこの『スレット アンド エラー マネジメント』を紹介しますのでしばしお付き合いください。
まず言葉の説明から始めましょう。
さて「スレット:Threat」とは何でしょうか? 直訳すると「脅威」という言葉なのですが、「航空機乗組員が直接関与していない領域で発生し、運航の複雑度が増すようなイベント又はエラーであり、安全マージンを維持するために対応されなければならないもの」(航空局通達より抜粋)と定義されています。
簡単に言うと、パイロットとは関係ないところで発生し、安全に影響を及ぼすような事象のことです。具体的には、悪天候、航空機システムの不具合、空港周辺の高い障害物、管制官や客室乗務員のエラー、タイムプレッシャーなどを指します。挙げればキリがないのですが、これらはパイロットのエラーを誘発する要因となるのです。
「エラー:Error」についても「組織又は航空機乗組員が意図又は期待する状態からの逸脱に至る航空機乗組員の行動又は無行動」(航空局通達より抜粋)と定義されています。エラーというと、何かを“やってしまった”という印象が強いと思うのですが、やるべきことをやらなかった場合も当然「エラー」となります。
航空機の運航現場では、刻々と変わる状況の中で常にさまざまなスレットに遭遇しています。そのスレットに対し「具体的な対策」を取りながら、エラーの発生を最小限にすること、そして、万が一エラーが発生しても、そのエラーがより「※航空機の安全レベルが低下した状態」へと悪化させないように「具体的な対策」を施しながら航空機を運航すること、この考え方が『スレット アンド エラー マネジメント』というものです。
※ 航空機の安全レベルが低下した状態(Undesired Aircraft State=UAS ):航空機乗組員 によって引き起こされ、安全マージンの低下を伴うような、航空機の位置や速度の逸脱、不適切に操作された操縦系統、誤ったシステムコンフィギュレーション(航空局通達より抜粋)

この考え方を分かりやすく表したものが【図】です。
もちろん、運航中に遭遇するすべてのスレットに対して何らかの対策を講じるわけではありません。状況を確認し、リスク評価を行いながら「何もしない」という選択も多々あります。ただし、安全運航へ何らかの影響が考えられる場合や、今後の状況変化によっては影響が予想される場合は、具体的な対応を取らなければなりません。
例えば、夕方の伊丹空港発、羽田空港着のフライトを考えてみましょう。天気の現況は大阪・東京ともに晴れですが、関東地方では夕方から大気の状態が不安定となり広い範囲で積乱雲(入道雲)の発生が予想されている、というような場合です。このような場合は、羽田空港到着時にゲリラ豪雨に遭遇してしまい着陸できない可能性があります。ですので、上空で雨雲の通過を待てる量の燃料を追加で搭載します。また、飛行計画の作成にあたっては、目的地空港に着陸できなくなった場合に備え、代替空港を選定するのですが、この代替空港も変更する可能性があります。好天であれば目的地・羽田の代替空港は通常成田空港を選定します。ところがこの例のように、関東一帯で積乱雲の発生が予想されている場合は、より好天が予報されている中部国際空港や出発地の伊丹空港を代替空港として選定し、その飛行ができる分の燃料をさらに搭載するわけです。このような対策を講じることによって、実際に悪天に遭遇しても「燃料は十分搭載しているし、羽田空港に着陸できない場合でも、より条件の良い空港へ向かうことができる」と思えることは、大きな精神的ゆとりを生みます。このゆとりこそが「ヒューマンエラー」を防ぐ最大の武器という訳です。
この例では、悪天が「スレット」です。そして「上空で待機できる分の追加燃料搭載」と「代替空港の変更」が「具体的な対策」となります。この「具体的な対策」を「対抗手段:Countermeasure」と呼んでいます。
残念ながら、悪天のように事前に認知できるスレットばかりではありません。地震や火山の噴火などの自然現象は、いつどこで発生するかを正確に予測することは不可能です。また、急な滑走路の閉鎖や急病人の発生など、突発的なスレットもあります。いずれにせよ「スレット」や「エラー」に「対抗手段」を講じることにより、「航空機の安全レベルが低下した状態」や「事故」を防ごうという考え方が「スレット アンド エラー マネジメント」です。
「やばい」を「スレット」と 表現しリスク要因を明確に共有する
この「スレット アンド エラー マネジメント」にはもう一つ大きなメリットがあります。それは「スレット」をチームで共有できるということです。レスキュー隊員の皆さんが活動される現場で「漠然とした不安」を感じたことはありませんか? この「漠然とした不安」は「暗黙知」と呼ばれるもので、これまでの経験や知識に基づいて生じるものです。この「暗黙知」は、言葉に表現して「形式知」にすることが難しい場合があります。この時「スレット」という言葉を使うと簡単に「形式知」とすることができるのです。そして「形式知」にできることにより、チーム内で共有することができるという訳です。
現場で風向・風速に何となく不安を感じたとき、「風がやばくない?」なんて言い方をしていませんか? 残念ながら、これでは相手に真意が伝わりにくいのではないでしょうか? こんな時に「スレット」という言葉を使ってみて下さい。「今日の風はスレットになるね」などと伝えれば、より詳細な状況認識から具体的な対策が取られやすくなると思います。
いかがでしたでしょうか? 今回は『スレット アンド エラー マネジメント:TEM』の概要をご紹介しました。このTEMは一人乗りの航空機でも行っています。また車の運転など、日常生活の中でも知らず知らずのうちに行っているのではないでしょうか。
次回はこのTEMを実践しながら、チームとしてエラーを防ぐ、具体的な行動についてご紹介したいと思います。そのキーワードは「ノンテクニカルスキル」と「MCC:Multi-Crew Co-operation」の二つです。「ノンテクニカルスキル」については、最近耳にする機会が増えたのではないでしょうか。一方の「MCC」はあまりなじみがない言葉だと思います。次回はこの二つについてお話しさせていただきます。是非ご覧ください。

石川 宗Ishikawa Hajime
日本航空株式会社
運航訓練部 調査役機長
(役職は連載誌面掲載当時のもの)