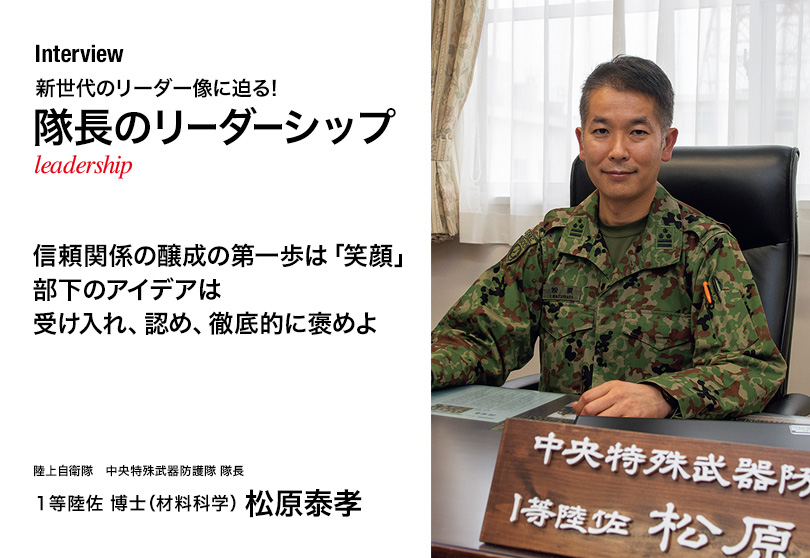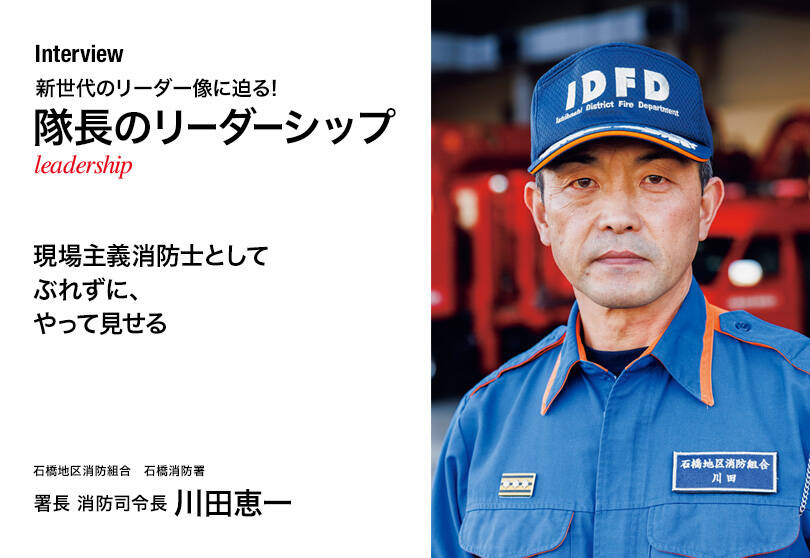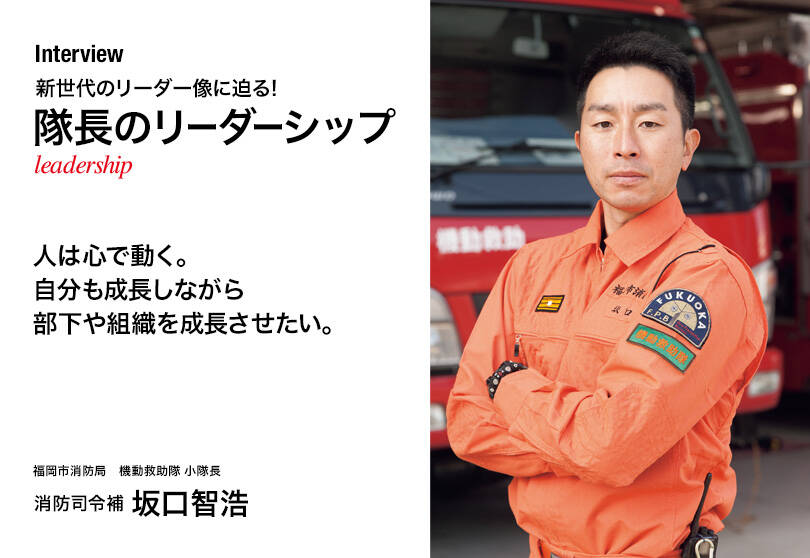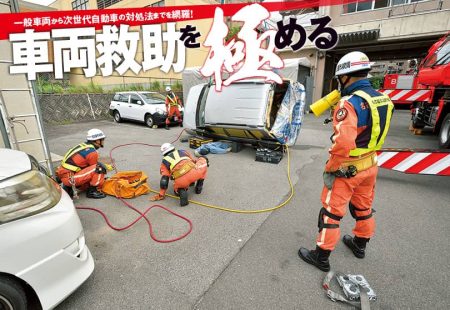髙野駿也
さいたま市消防局 警防部警防課 装備係 消防副士長 髙野駿也
Interview
消防車両づくりは、イマジネーションが大切
装備担当者の仕事
大規模な消防本部の消防車両づくりは、どのような考えに基づいて行われているのか? 小型ポンプ車や救急車、救助工作車、特殊車両など毎年何台も発生する更新車両を、ゼロ知識から作り上げてきた高野駿也担当に、装備の現場、車両づくりの極意を伺った。
写真·文◎伊藤久巳(車両写真◎さいたま市消防局提供)
Jレスキュー2021年9月号掲載記事
280台の車両を毎年約25台更新
1車種をメインとサブの2名が担当
「局全体では約280台の車両がある」
これだけの車両を擁するさいたま市消防局。その車両たちの更新計画を一手に担うのが警防部警防課の装備係だ。装備係では車両更新ばかりでなく、車両の保守や修理、さらには局全体で使用する資機材の更新と修理に関することまで、あらゆる装備を担当する。
装備係は係長以下計5名でチームを構成。車両だけについて言えば、毎年25台前後のペースで更新計画が推移している。局内の車両更新基準はポンプ車が13年経過後、救急車が7年経過後かつ走行距離15万km以上に達した段階、救助工作車が15年、はしご車が17年などと定められており、装備係では約5年先まで年度間ごとのスケジュールを立てて更新計画を実行している。近年は更新時期の重なりにより特殊車両の更新が立て続き、令和元年度の更新車両には後方支援車や指揮支援車、先端屈折式はしご車などがあったほか、令和3年度は特殊災害対策車や水難救助車などが含まれている。また、救助工作車は令和2年度から管内各消防署で毎年更新が続く計画が組まれている。
装備係ではどのような車両であっても更新車両の担当はメインとサブの2名体制で担当することになっており、基本計画から仕様書作成、車両製作業者との打ち合わせを経て中間検査、完成検査、納車に至るまで、継続して2名の眼で作り込むことにより、担当者1名では気づけないことがあればカバーできる体制がとられている。
30m級先端屈折式はしご付消防自動車
さいたま市消防局 岩槻消防署

〈SPEC〉
車名/日野◎通称名/プロフィア◎シャーシ型式/2DG-FR1AJA改◎全長/10730mm◎全幅/2490mm◎全高/3400mm◎ホイルベース/不明◎最小回転半径/7.8m◎車両総重量/19170kg◎乗車定員/6名◎原動機型式/A09C◎総排気量/8860cc◎駆動方式/6×2◎はしご最大地上高/30m(5連)◎梯体装備/先端屈折式、先端伸縮式、伸縮水路管◎配備年月日/令和2年3月26日◎艤装メーカー/モリタテクノス
製作スケジュールよりも前から
何度も現場に足を運ぶ
車両製作のスケジュールは、製作年度の前年にスタートする。前年の春から夏にかけてある程度の方向性を決定し、夏から冬にかけて仕様書を作成していく。並行して、その秋には予算編成を行い、冬には該当する車両の緊急消防援助隊設備整備補助金要望を行う。そして、製作年度の春には入札により車両製作業者が決定し、打ち合わせを重ねながら秋頃から冬にかけては中間検査、さらに打ち合わせを重ねながら年度末に完成検査を経て納車し、各消防署所に配備、取扱説明を行う流れになる。
さいたま市消防局の場合は、車両更新計画が大枠で5年先まで決まっているため、実際には前年の春に正式にスタートするよりも前から始まっているといえる。
「製作年度の前年には更新車両のイメージをある程度固めておく必要があるので、製作年度の前々年の夏あたりから前年には事務仕事の合間を縫って各消防署所に出向して隊の意見を聴く。実際に使ってどうかが大事、隊員から生の声を聴いてよくしていきたい。電話でなく直接話せば、他愛もない話から本音も聴ける。そして、冬にかけてある程度まとめておいた上で、前年の夏頃に仕様書の作成を開始する」
髙野主事は警防部警防課装備係に配属されて今年で4年目(取材当時)。消防車両づくりのいわばベテランと呼べる域にある。装備係員がメインとして担当する車両は年間だいたい4〜5台だが、髙野主事が令和3年度に担当する車両は救助工作車1台、水難救助車1台、指揮車1台、支援車Ⅲ型1台、そしてはしご車のオーバーホールが1台の計5台だという。そのどれもが「右から左」というように簡単にはいかない車両たちだ。装備係配属当初は髙野主事もそうだったように比較的シンプルな構造のポンプ車の車両製作から始め、2年目、3年目以降は救急車、救助工作車、はしご車などへと進んでいくが、すでに配属4年目ということから、このようないわば製作が難関な車両の担当となっている。
「このほかにも、資機材として電磁波探査装置等の更新も担当しているため、けっこうヘビーではある(笑)」
これら5台は本誌が発売される頃に前後して製作打ち合せが着々と進められているが、その中では水難車のスタートがもっとも早かったという。
「水難救助車は2年前から調べ始めた。局に1台しかない特殊な車両で、だからといってそれを理由に絶対に失敗は許されない。これから15年以上使用することもあり、やれることは全部やりたいと考え、はしご昇降装置を応用してボートを電動で積載できるよう進めた。電動式は消防車両で初めての試みとなるが、自分が以前、水難救助隊として乗務した経験から、クレーンでの吊り上げは時間がかかり、ボートを上げ降ろしするために隊員が毎回車上に乗ることは危険だと感じていた。地上から降ろせた方が格段に現場活動が迅速で安全だ」
取材に訪れた日は、髙野主事が今年度メインで担当する車両の打合せを納入業者と行う時期にあり、そのどれもが製作の一歩目にあたるところだった。
「実は装備係配属当初、私は車のことにあまり興味がなかった。それまでの消防人生では与えられた車両をただ使うだけで、詳しいことはあまり知らなかった」
だが、人事異動の日を境に、車両を知らないでは済まない日々がやってきた。知る知らないに関係なく、業務命令により車両を製作していかなければならないのだから。
「装備係の先輩からは、『まず車両に興味を持て』と言われた。そして、手取り足取り教わった。自らも近くの消防車両艤装会社をはじめ、市内各署所、その他いろいろな場所に足を運んで消防車両を見せてもらった。時には他の消防本部にも。できることは全部やった。車両に喰らいついてきた。知らないからこそ聞けるし、まっさらだから恥じることもなく聞けることもたくさんあった」
それまで本気だった陸上の救助、そして水難救助から、髙野主事は装備係の先輩の言葉どおり車両製作に本気で向き合ったのだ。
「とんちんかんなことをやると災害での車両運用、さらには現場活動に直接響いてくる。最初は先輩がいてくれて本当によかった。その後は見て感じて覚えていった」
指揮支援車 さいたま市消防局 警防課


〈SPEC〉
車名/日産◎通称名/シビリアン◎シャーシ型式/ABG-DVW41◎全長/5990mm◎全幅/2100mm◎全高/3000mm◎ホイルベース/3310mm◎最小回転半径/6.0m◎車両総重量/5245kg◎乗車定員/7名◎原動機型式/TB45◎総排気量/4470cc◎駆動方式/2×2◎配備年月日/令和3年3月14日◎艤装メーカー/平和機械
次のページ:
車両製作は常に金銭管理とともにある