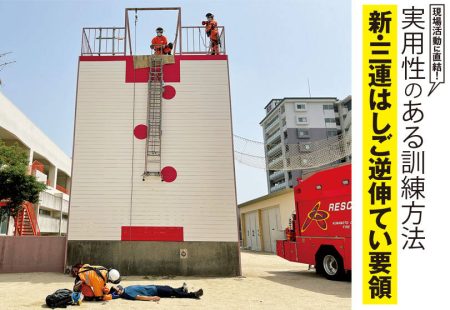支援車Ⅳ型
金沢市消防局
金沢市消防局 警防課[石川県]
文◎橋本政靖 写真◎金沢市消防局
日本の消防車2019掲載記事
金沢消防が本気で考えた
通常災害から緊援隊まで使える「進化形指揮車」誕生
他都市に出場する警防車
消防の指揮隊には消防署で運用するもののほかに、本部が運用する指揮隊がある。金沢市消防局では、建物火災以上の火災、特異な火災、救助および事故においては必要に応じて局指揮隊が出動し、消防署指揮隊が開設する「消防現場指揮所」運営の支援活動や情報収集を行う。
さらに災害が大規模になった場合、消防局が開設する「消防現場本部」運営の主体となり、各消防署指揮隊とともに包括的な指揮活動を行う。また、大規模な災害が発生した際には、緊急消防援助隊石川県大隊の都道府県指揮隊および統合部隊指揮隊として出動する。
2007年(平成19年)以来10年ぶりに更新された同車は、平成20年度の緊急消防援助隊法制化以降、金沢市消防局としてははじめて他都市への出動を前提とし、通常の災害での指揮活動や緊援隊出動時の2通りに活用できるよう作成された。特装・寒冷地仕様として、さまざまな事案に対応できる車両である。


3波同時受信・2波同時送信で指揮能力が飛躍的に向上
車両のベースはトヨタ・ハイエースの最大級サイズであるワイド・ハイルーフ・スーパーロングで、後部室内サイズは長さ3500mm×幅1700mm×高さ1600mmと、高規格救急車であるハイメディック並。このスペースを有効活用して、乗車スペースと資機材収納スペースが作られている。
まず、室内の装備について見てみよう。指揮車の命ともいえる情報収集用の作業卓は、床面から天井まである棚と一体化したタイプを採用。上部に無線機類、情報収集用TV(10型)、机上には大型警戒表示板操作装置およびコピー機能付プリンタ、机前方にはAVM端末と、指揮活動に必要なすべての情報がここに集約される。
今回飛躍的に向上したのが、情報収集能力である。単信式・複信式消防デジタル無線機、消防デジタル受令機の3台で、最大3波同時受信・2波同時送信ができるようになった。
無線機通話口は作業卓左側に設置し、車内でも車外の指揮本部でも発信しやすいように配慮している。通話内容は車内上部スピーカーから放送されるだけでなく、使用頻度の高い単信式消防デジタル無線機は、車外サイレンから放送して現場隊員全員で共有できる。
また、車外の指揮本部をサポートする工夫もなされている。スライドドア開放部の作業卓側壁面に住宅地図やハンドメガホン、拡声マイクを設置し、車外からすぐにアクセスできる収納スペースとした。さらに、指揮台で使用する無線類はユニット化して積載。取っ手付の台座に機器類が据え付けられているので持ち運びやすく、車両後部の単信式消防デジタル無線機と有線接続するだけで使用できるようになっており、迅速な指揮本部構築を実現した。
外観





荷室はこんなに有効活用できる!
後部座席シートは、座面および背もたれが反転可能なクロスシート。床面スライドレールが敷かれていて3人がけ×2列のシートを移動させ、シートアレンジにより4種類の使い方ができる。等間隔で前向きに設定すると3名×2列で前向きに着座する乗車モード、シートを折りたたんで片方に移動させることで床面がフラットな積載スペースとなる資機材搬送モード、向かいあわせにすることで打ちあわせが行える作戦会議モード、フラットにすることでベッドとなり、後方支援モードとして仮眠休憩スペースにもなる。
資機材積載スペースは、荷室にウォークスルー方式を採用して十分に確保した。荷室左右にそれぞれ役割の異なる資機材庫を設置し、後部座席からリアハッチまで通り抜けられるようになっている。近年はリアハッチ開口部を全面資機材庫とした車両が主流になっているが、積載位置がほぼ固定されているうえ、後部座席側からしか荷室にアクセスできないため、不測の荷物を載せるのに難儀する。ウォークスルー方式とすることで棚の間をフリースペースとして追加資機材を積載できるし、入口を大きくとっているため大きな荷物や長尺物でもかんたんに入れることができるのだ。ここに荷物を載せきれない場合、車両上部に設置されたルーフキャリアに積載する。
後席





シートモードのバリエーション



次のページ:
サブバッテリーで充実のギミックをサポート