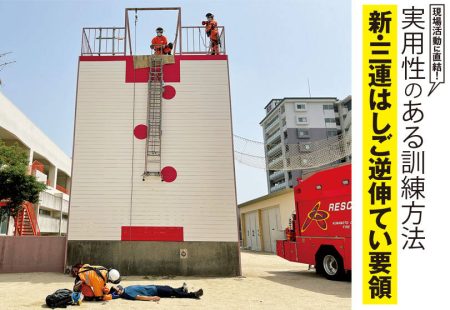水槽付消防ポンプ自動車I-B型
福岡市消防局
福岡市消防局 東消防署多々良出張所[福岡市]
写真・文◎小貝哲夫
Jレスキュー2016年3月号掲載記事
化学車I型からタンク車へ
福岡市消防局では昭和62年以降、更新時期を迎えたタンク車に代えて、順次化学車I型(水槽容量1000L)を5台配備してきた。当時管内では九州自動車道などの交通インフラの整備が進み、それに比例して車両火災やトンネル火災、加えて小規模な油火災が増加していたからだ。
ところが運用を開始してみると、薬剤(泡原液)を用いた消火活動の実績は極めて少なかった。水とは違い、薬剤を使った場合は放水後に処理作業が必要になるが、そのための訓練場所が限られ、隊員たちは泡消火活動の習熟度を上げる機会を得られずにいた。そのため、命がけの現場での泡消火という選択肢は採用されにくかったのである。またタンク車の代役として使うには、積載水の容量にも不安があった。
そこで同局は車両の見直しを行い、化学車I型5台をCAFS装置搭載のタンク車に置き換えることにした。化学車の導入理由だった車両火災と小規模な油火災はCAFSで対処でき、1500L水槽を搭載すれば活動に使う水量も十分だと考えたのだ。
今回紹介するタンク車は、見直し後の第一号として2015年(平成27年)6月5日に東消防署多々良出張所に配備された、記念すべき1台だ。

大所帯ならではの事情
取材当時、人口153万人を擁する福岡市は、九州地方の政治・経済・文化の中心地。その安全を守る同局は、1消防本部7消防署1消防航空隊で市内全域をカバーし、職員数は1050名、消防車両数は実に222台にのぼる大所帯だ。人員の異動だけでなく車両の配置転換も頻繁に行っているため、新車両にはどこの署に配置されても使いやすい汎用性が求められた。
同車の製作を担当した矢野消防司令補(取材当時)は将来の展望をイメージし、現場隊員の意見を参考にしながら汎用性と機能性を兼ね備えた車両をめざした。ただ、現場の声を受け入れすぎると機能性は上がっても汎用性がなくなるケースが多い。そこで、すでに現場を離れたベテラン隊員の意見も汲み取り、放水関係の操作性向上と収納力アップを基本コンセプトに据えて仕様書を練り上げていった。

吸管位置を後部に
完成した同車の大きな特徴のひとつが、吸管の取り付け位置だ。同局保有のポンプ車の多くは吸管を左右両側のポンプ室に配置しており、現場からはコック類を操作する際に邪魔になったり、放水後の吸管操作が難しいという声があがっていた。そこで同車では思い切って吸管をポンプ室から取り去り、後部積載庫に配置することにした。これはベテラン隊員の「昔の消防車は使いやすかった!」という意見を参考にしたものだ。しかも巻吸管は左側1本のみとし、2本目は棒吸管(3m×1本、3.5m×2本)を車上に収納することにより、さらに資機材の収納スペースを確保することができた。
次に、これまで別々にあった中継口と吸水口を中継吸水口に一本化することで配管を削減した。配管が減ったことで、積水口が後輪フェンダー内からポンプ室内へと移設可能となり、吸水・中継・放水をポンプ室内に集約することができた。これらの工夫により、操作盤まわりの操作性がぐっと向上した。
こうしたコンパクト化によって、ポンプ室の上部に余剰スペースが生まれ、結果的に収納スペースアップにも繋がった。ここは貫通式の大容量収納スペースとなっている。
車上






次のページ:
使用頻度に配慮したレイアウト