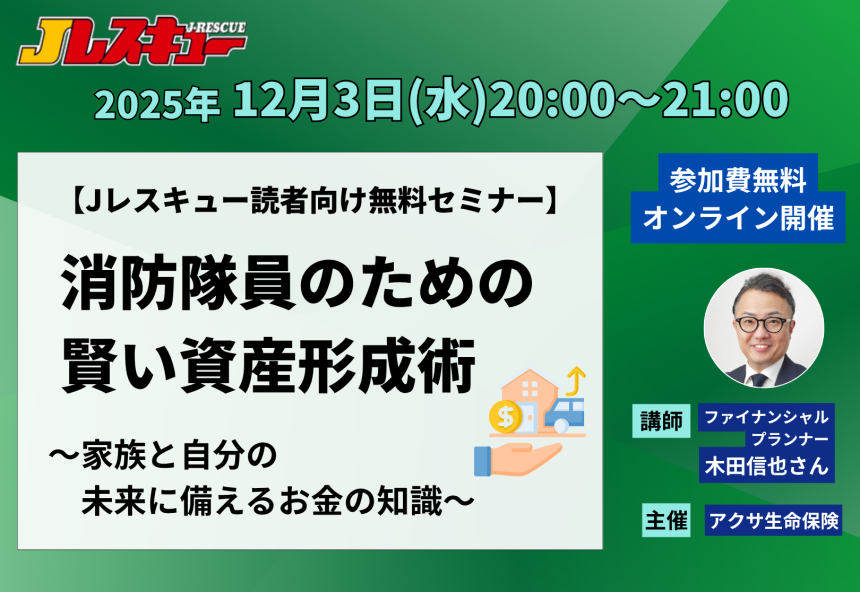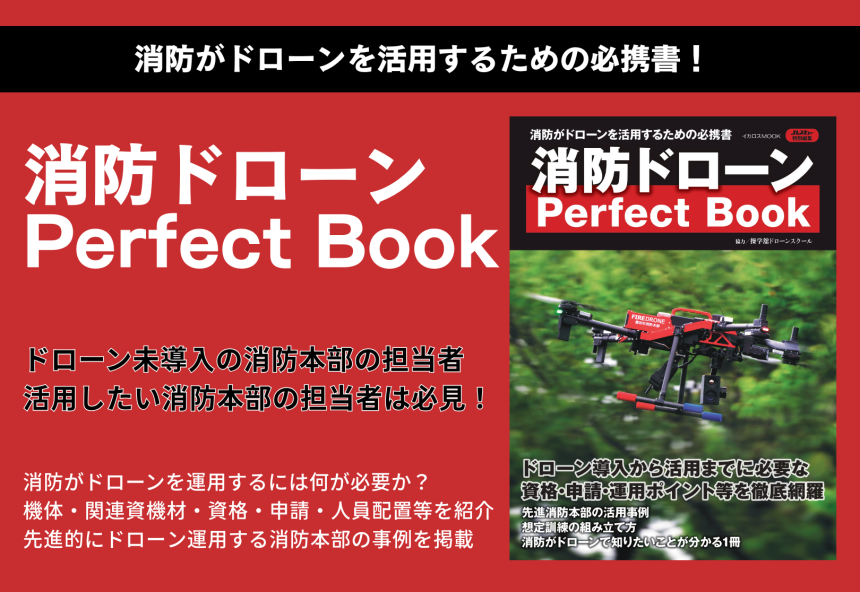News
【コラム】光り方にも歴史あり「赤色灯のはなし」
消防自動車をはじめとする緊急車両は(赤色)警光灯とサイレンを用いて緊急走行を行う。この際の警光灯は現在ではLED式のフラッシュタイプが主流となっているが、どのような法令に基づいてどのように進化してきたかを見てみよう。
写真・文◎橋本政靖
Jレスキュー2019年5月号掲載記事
戦後間もなくから昭和40年代頃までに制作されたドラマや映画などでは、車両フロント上部付近にフォグランプのような赤色の灯火をつけたパトカーや消防自動車を見ることができる。
法令によると、警光灯は必ずしも回転したり、点滅させなければいけないわけではない。緊急車両に設ける警光灯は、道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号)第49条1に「警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。」とされている。つまり、前方300mから視認できる赤色の灯火であればよいのである。そのため昭和30年代頃の緊急車両には、前方に向けて赤色が連続点灯している灯火が設けられているのみであった。
しかし、交通量の増大や一般車両の遮音性向上により、事故防止等の観点から視認性の高い警光灯に進化する必要が出てきた。これが昭和30年代中ごろに登場し、急速に広まった筒型の回転型タイプである。昭和50年代には散光式、平成6年頃には湾曲型(ブーメラン型)と発光面積が増えていき、視認性は著しく向上した。
さらに平成10年頃には光源がそれまでの電球式からキセノンフラッシュ式に、平成15年頃には現在主流となっているLED式が登場。高輝度タイプが多数登場し視認性が向上するだけでなく、側面取り付けや点滅方式を様々に変えることができる方式など、点灯方式についても進化している。だが一方で眩しすぎるといった問題も生じており、減光や一部消灯などの機構を設ける場合もある。
10年ごとに進化していく赤色警光灯。今後はどのような新しい機構が登場するのかが楽しみだ。